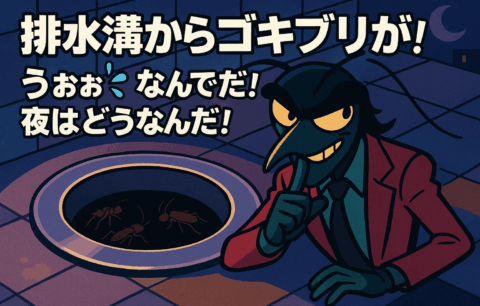パソコンのキーの隙間から「パチッ」とかすかな動きを感じたり、画面の端に黒い点がチラチラしたりすると、何の仕業かとビビッてしまうものです。
とくに梅雨どきや夏の高温多湿期は、チャタテムシなどの小さな害虫がパソコン内部のわずかな隙間に入り込み、カビやホコリを“ごちそう”にして繁殖しやすい環境になります。
放置すればキーボードの入力不具合を招くだけでなく、熱を持った基板の冷却を妨げ、最悪は長期的な故障につながりかねません。
ここでは、なぜパソコンに虫が入り込みやすいのかを解説し、即効でできる駆除法から再発防止策までをくわしくご紹介します。
パソコンに虫が侵入する3つの理由
まずは虫がパソコンを“住処”に選ぶ背景を押さえましょう。
1.隙間だらけの入り口
液晶とベゼルのわずかなすき間、キーキャップとキーボードベースの間、USBポートや通気口。
パソコンは外見こそピッタリ組まれているようですが、実はミクロンオーダーの隙間が点在しています。
そこから体長1~2ミリのチャタテムシやノミバエの幼虫、あるいはシバンムシがスルリと入り込むのです。
2.内部の“快適空間”
パソコンの内部基板は作業中に発熱し、熱を逃がすためにファンが回転します。
ファン周辺はほんのり暖かく、湿気もこもりやすい。
カビをえさとするチャタテムシにとって、まさに楽園です。
3.ホコリと食べカスのごちそう
デスクでの飲食のあと、パン屑や飲み物の飛び散りがキーボードの隙間に入り込むと、虫の栄養源になります。
掃除機の届かない細かいホコリもエサ場になるため、虫が繁殖してしまうのです。
電源オフ・冷却してから始める安全な駆除手順
※自分でできる範囲で行ってください。
パソコン内部は精密機械。
濡らさず、静電気を帯びない対策が必須です。
ステップ1 完全シャットダウンと電源ケーブル抜き
電源を落としたらACアダプタやUSBケーブルを抜き、バッテリー着脱可能モデルは外しておきます。
ステップ2 本体の十分な冷却
動作直後は内部が高温です。
30分ほど放置し、タッチして熱さを感じなくなるまで待ちましょう。
ステップ3 外装・画面クリーニング
無水エタノールを液晶専用クロスに少量湿らせ、優しく画面や天板を拭きます。
水分は一切禁止。クロスは固く絞ってください。
ステップ4 キーボード&ポートまわりの虫取り
粘着クリーナー(粘着ローラー)でキー上面を転がし、ホコリと付着虫を回収。
キーとボディの隙間は、掃除機のパイプのみを使って吸引します。
ノズルを付けると勢いで虫を奥に押し込む恐れがあります。
ステップ5 内部ホコリの吹き飛ばし(自信がある場合のみ)
底面カバーを外せるモデルは、エアダスターで内部のホコリを奥から手前へ吹き飛ばします。
連続噴射は冷却水を生むので、1秒ずつ短く吹きましょう。
内部クリーニングに不安がある場合は、この段階は専門業者に任せてください。
常に清潔・快適を保つ4つの再発防止策
一度駆除しても、環境が変わらなければすぐ再発します。
日々の習慣で侵入を阻止しましょう。
対策1 机まわりは“絶対に”飲食禁止!
パソコン本体だけでなく、デスク全体をクリーンゾーンに。
飲み物は蓋付きボトルへ、食事は別のテーブルで済ませる習慣を。
対策2 週1回のキーボード&本体外装掃除
粘着クリーナーとクロス拭きだけで、ホコリも虫の卵も減ります。
こまめな掃除が最強の予防策です。
対策3 定期的な換気と除湿
湿度60%超はカビ・虫向き。
除湿器やエアコンで50%以下を保ち、窓を1日1回開けて空気を入れ替えましょう。
対策4 防虫カバーやシリカゲル併用
使用しないときは専用カバーをかける。
内部の湿気対策にシリカゲル(乾燥材)を小袋で周囲に置くのも効果的です。
専門業者に依頼すべきタイミング
自力で掃除しても真っ黒なホコリや虫が次々現れる、動作不良や異音が直らない場合はプロにお任せを。
内部まで徹底的に分解清掃し、防虫・防塵コーティングを施してくれるので安心です。
パソコンに入り込む小さな虫は、放っておけば機器の寿命を縮める元凶。
電源オフ・完全冷却のうえ、無水エタノール拭き、粘着クリーナー、エアダスターで徹底駆除し、湿気管理と清掃習慣で侵入をシャットアウトしましょう。愛機をいつまでも快適に使い続けるために、日々のひと手間が何よりの防御策です。