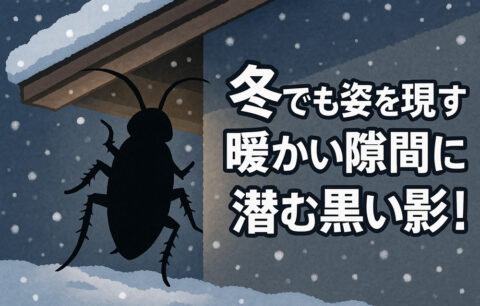じめじめした季節には、窓を開けるたびに「むわっ」と湿り気を含んだ空気が部屋に流れ込みます。
そんなとき、ふと足元の隅に黒々とした細長い影を見つけた瞬間の背筋の凍るような恐怖。
ムカデが出ると聞くだけで、夜にトイレに行くのも億劫になってしまう方は多いでしょう。
ムカデは毒を持ち、人を噛むこともあるため、「いつ、どこで」出るのかを知っておくことが、安心して過ごすための第一歩です。
本記事では、ムカデが最も活発に動く時期を季節ごとに詳しく解説し、家の中で遭遇しやすい場所や予防策まで、具体的なポイントを押さえてご紹介します。
これを読めば、ムカデの動向が手に取るようにわかり、恐怖から解放された快適な暮らしを実現できるはずです。
春から初夏(5月~6月):活動再開と梅雨の湿気が追い風
春の訪れとともに、冬眠から目覚めたムカデは5月ごろから活動を再開します。
特に梅雨入り前後の5月下旬から6月は、気温が20℃以上、湿度も上昇し始めるため、ムカデにとって過ごしやすい環境が整います。
冬眠から覚めたムカデの動き出し
冬の間、地中や石の下でじっと冬眠していたムカデは、暖かい気温を感じ取るとともに巣穴を這い出し、周辺を徘徊し始めます。
土の湿り気を頼りに動き回り、エサとなる小昆虫を求めて徐々に行動範囲を拡大します。
家の外壁や基礎まわりのひび割れ、玄関まわりの植え込みなど、地面と建物の隙間は格好の通り道です。
梅雨時の高湿度が生息条件を整える
梅雨入りすると、湿度が70%以上に達し、土壌やコンクリート表面にも水分が染み込みます。
ムカデは乾燥に弱く、ジメジメとした場所や水滴が伝う壁面を住処に選びやすくなります。
特に雨が降り続く夜間には、家屋のわずかな隙間から室内への侵入チャンスを狙ってくるため、梅雨時の夜の玄関周辺は要注意です。
夏(7月~8月):猛暑下の夜間活発化と隠れ家探し
真夏の昼間は気温が30℃を超え、直射日光を浴びるとムカデも動きを控える傾向があります。
しかし、夜になると気温が下がり、湿度も高まるため、ムカデの活動は一気に活発化します。
昼間は涼しい隠れ家で休息
日中のムカデは、庭の植木鉢の裏やガレージの物置足元、玄関ポーチの段差下など、直射日光を避けつつ湿度を保てる場所で休息しています。
これらの場所は人の目に付きにくく、捕食者から身を守るにも適しています。
夜間の徘徊と侵入チャンス
夜9時以降になると気温が25℃前後に下がり、湿度が80%を超えることも。
ムカデはこの時間帯に活動のピークを迎え、家の壁面を這い上がって小さな隙間を探し、台所や浴室の床下、押入れの奥などへ忍び込みます。
寝室付近の引き戸や畳の継ぎ目も要注意ポイントです。
エサ場となる昆虫が集まる場所を狙う
ムカデは動きの遅い昆虫やクモなどを好み、街灯周りや玄関外の虫除けライトに集まる虫を狙って徘徊します。
街灯に群がる蚊や蛾を追うように家屋の壁を上がり、そのまま窓枠の隙間や換気口から室内に入り込むケースも少なくありません。
秋(9月~10月):子ムカデの巣立ちと二次繁殖期
9月に入ると、梅雨時期に産み付けられた卵から孵化した子ムカデが成長し、単独で活動を始めます。
そのため、秋は成体だけでなく子ムカデの姿も多く見かける、二次的な繁殖期に当たります。
子ムカデの脱皮・成長と食欲の増加
春に産卵された卵は、6~8月の暖かい環境で孵化し、数回の脱皮を経て9月には体長数センチの子ムカデに成長します。
成長期のムカデは非常に食欲旺盛で、餌を求めて広範囲を徘徊するため、庭先だけでなく室内へも頻繁に出没します。
涼しい気候で日中も活動する個体が増加
夏と比べて日中の気温がやや下がる秋は、ムカデが昼間でも行動しやすい気候になります。
特に曇天の日や雨上がりの曇雨天が続いた日は、昼間に湿度が高い状態が続くため、浴室のタイル床や洗面所周辺などを歩き回る姿が見られることがあります。
繁殖直前の強烈な行動範囲拡大
成体のムカデは秋に交尾し、10月末から11月初旬に卵を産み付けます。
その準備として、交尾相手を求めて遠くへ移動する個体も増えるため、庭や家屋周りのあらゆる隙間に注意が必要です。
晩秋から冬(11月~3月):冬眠と減少期
11月を過ぎると気温が10℃以下に下がり、ムカデは徐々に冬眠に入ります。
家屋に侵入した個体も、床下や壁内のわずかに暖かい隙間に潜み、春までじっと息をひそめます。
冬眠先として好まれる暖かい場所
床下の断熱材裏や土間コンクリートと根太(ねだ)の隙間、温水パイプの周辺など、微妙に暖かい空間はムカデの冬眠場所として最適です。
室内にまで侵入すると、押入れ奥や家具の下なども冬眠先になりえます。
冬季は温度差でちらほら目撃も
真冬でも室内の暖房や家電の送風口、暖房器具周辺などに集まる個体が見られることがあります。
こうした冬眠途中のムカデは動きが鈍く、人が踏んでしまう危険性もあるため、掃除や収納作業時には足元に注意しましょう。
ムカデに遭遇しないための家の対策
ムカデを活発期に見かけないためには、家の周辺と室内両方で「湿気対策」「隙間封鎖」「衛生管理」「検知アイテム活用」の4つを徹底しましょう。
湿気を抑える換気と除湿の習慣
キッチン、洗面所、浴室などの水回りは、使った後に必ず換気扇や窓を開け、湿度を下げます。
梅雨や夏期はエアコンのドライ運転や除湿機を活用し、湿度を60%以下に保つことで、ムカデが好む高湿度環境を作らせません。
隙間封鎖で侵入経路を断つ
庭と家屋の境界、配管スリーブ周辺、玄関ドア下のクリアランス、窓サッシのすき間など、数ミリの隙間もムカデ侵入のチャンスになります。
防虫コーキング材や隙間テープでしっかりふさぎ、家全体をシールするように封鎖しましょう。
清掃と衛生管理でエサ源と隠れ家を断つ
落ち葉や枯れ枝、植え込みの下草はムカデの隠れ家。
定期的に庭の掃除を行い、植木鉢や段ボールなども放置せず整理整頓します。
室内では食べこぼしやホコリ、木くずを掃除機で吸い取り、ムカデのエサとなる害虫を減らしましょう。
検知アイテムで早期発見を実現
粘着式トラップや侵入検知シートを、庭の植え込み付近や家屋の基礎まわり、室内の押入れ下などに設置しておくと、ムカデの侵入をいち早くキャッチできます。
週に一度チェックし、かかった個体を即処分することで繁殖前に補足できます。
専門業者への依頼タイミングと選び方
自力対策でもムカデが減らない、または大量発生して手に負えない場合は、速やかにプロに依頼しましょう。
自力対策の限界を見極めるポイント
一月以上、湿気・隙間封鎖・清掃を徹底してもムカデを見かけ続ける、あるいは巣穴が家屋の基礎や床下に複数ある場合は要注意。
見えない床下や壁内に巣を作られている可能性が高くなります。
信頼できる業者の選び方
依頼時には
(1)ムカデ駆除の実績が豊富、
(2)薬剤や罠の種類を説明してくれる、
(3)施工保証やアフターフォローがある、
(4)見積もりが無料かつ追加費用の説明を明確にする、の4点を確認しましょう。
複数社に見積もりを取り、比較検討するのがおすすめです。
ムカデは春の温暖化と湿気の増加を機に冬眠から目覚め、夏の夜に活発化し、秋には子ムカデが加わって二次的繁殖期を迎えます。
暖かく湿った場所や隙間を探し、家屋内外に侵入経路をつくるため、季節ごとの動向を理解し、湿気対策・隙間封鎖・清掃・検知アイテムを四つ巴で実践することが、ムカデ遭遇リスクを大幅に減らす鍵です。
自力対策で不安な場合や大量発生時は、信頼できる専門業者の力を借り、被害を迅速に抑えこみましょう。
この記事を参考に、ムカデゼロの快適な暮らしを手に入れてください。