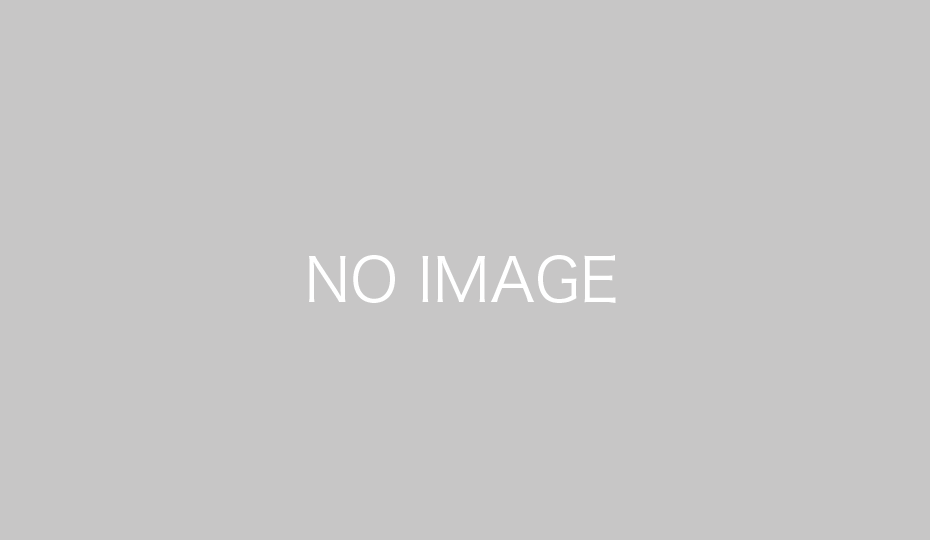「最近床下から小さな砂のような粉が落ちてくる…」「床下から“カリカリ”という音が聞こえて不安…」といった悩み、ありませんか?見えない場所でアリが巣を作っていると、家の構造材を痛めたり、シロアリ被害と勘違いして大きなリフォームが必要になるのではと心配になりますよね。放置すると建物の耐久性を損ない、最悪は床のきしみや沈下につながることも。この記事では、床下にアリの巣ができる原因から発見のサイン、具体的な駆除方法、そして再発を防ぐ予防策までを詳しく解説します!
床下にアリの巣ができる原因
床下にアリが巣を作る要因は主に「環境」「エサ」「侵入経路」の3つに集約されます。これらを理解することで、効果的な予防策を立てられます。
湿気と木材の条件
床下は地面からの湿気が上がりやすく、通気不良になると湿度が高止まりします。多くのアリは湿気を好み、腐食した木材や断熱材の間に巣を作ります。特に木造住宅で床下がコンクリート基礎と直結している場合、木部の含水率が上昇しやすく、腐朽菌とともにアリの住処となりやすいのです。
- 補足:含水率20%以上の木材はアリやシロアリが好む状態です。
エサとなる有機物の存在
床下に残された木くずや古い防湿シート、紙類、床材の切れ端などはアリの好物。有機物が豊富だと女王アリが産卵しやすく、コロニーが急速に拡大します。また、キッチンから漏れた食べかすが床下に流れ込むケースもあり、アリのエサ場を作り出してしまいます。
- 補足:食べかすは見えにくい場所に落ちやすく、発見が遅れる原因に。
外部からの侵入経路
アリは1mm以下の隙間でも通過可能です。基礎のひび割れ、配管周りの貫通部、点検口の隙間などから侵入し、床下全体に蟻道(ぎどう)を張り巡らせます。特に古い住宅では基礎コンクリートの目地が劣化している場合が多く、点検口周辺からの侵入が顕著です。
- 補足:侵入経路を物理的に封鎖しないと、駆除後も再侵入のリスクが高まります。
床下に潜む主なアリの種類と特徴比較
床下で見かけるアリは複数の種類があり、駆除方法やリスクが異なります。代表的な3種を比較表で確認しましょう。
| アリの種類 | 生息環境 | 被害特徴 |
|---|---|---|
| クロアリ | 湿気の多い土壌近くの木材や断熱材間 | 食べかすや甘いものを好むが、木材は食害しない。数が多いと建築物内部への侵入が問題に。 |
| イエヒメアリ | キッチン近くの隙間、暖かい場所 | 食品汚染リスクが高く、行列をなしてエサ場を拡大。毒餌が有効。 |
| シロアリ | 完全な土壌接触の木材、床下の湿潤部 | 木材内部を食害し建物構造を破壊。木部処理+土壌処理が必須。 |
クロアリとイエヒメアリの違い
クロアリは土壌中の有機物を分解する役割もありますが、住宅内では食品汚染を引き起こします。一方、イエヒメアリは都市部に適応し、数百匹のコロニーで家中を行進するため、迅速なベイト剤配置が必要です。両者とも薬剤散布とトラップが効果的ですが、クロアリは寒冷地でも繁殖するため、年間通じた対策が欠かせません。
シロアリとの見分け方
シロアリは「羽アリ」と呼ばれる有翅(ゆうし)アリを夏に飛ばし、巣の存在を知らせます。一般的なアリと違い、翅を落とした後に木材を食べ進むので、表面に蟻道(泥の通路)ができるのが特徴。蟻道が見つかったらすぐに専門業者へ相談しましょう。
床下のアリの巣を発見するサイン
適切なタイミングで巣を発見し対応すれば、被害拡大を防げます。以下のサインをチェックしましょう。
木材の粉状排出物(フラッシング)
アリが木材を穿孔すると、内側の木くずや排泄物が粉状で周囲にこぼれます。床下点検口の周辺や大引き(おおびき)の上に小さな粉が溜まっていたら要注意です。
- 補足:粉が湿っている場合、侵入直後の活動が活発である証拠です。
蟻道(ぎどう)の発見
アリ専用の通路である蟻道は、土やシロアリ由来の泥が混ざった細長い道です。コンクリートや木部表面を這う形で見られます。蟻道の長さや太さでコロニーの規模を推測できます。
- 補足:蟻道は再発防止のポイント。完全に除去しないと同じ経路を使われます。
「カリカリ」音や動く姿
夜間に「カリカリ」という乾いた音がする場合、アリの活動音かもしれません。また、点検口から懐中電灯を照らすと、小さな影が動いているのが見えることも。見えにくい場所は高倍率ライトと鏡を併用すると発見率が上がります。
- 補足:カリカリ音は木部齧り音だけでなく、蟻道を壊す音の場合もあります。
床下のアリの巣を駆除する方法
アリ駆除は「DIY」と「プロ依頼」の2つに大別されます。状況に合わせて選びましょう。
DIY駆除の手順とコツ
- ベイト剤の設置
糖分やタンパク質を好むアリ用の毒餌を蟻道に沿って点置き。女王アリが巣に持ち帰り、コロニー全体に薬剤が行き渡ります。- 補足:雨水で流されない屋内用ベイト剤を選びましょう。
- 蟻道の破壊と薬剤散布
残った蟻道をヘラやブラシで壊し、薬剤(粉剤/スプレー)を直接塗布。隠れた女王や兵隊アリにも効果を及ぼします。- 補足:粉剤は風で飛散しやすいので、養生フィルムを敷くと安心。
- 再発チェックと追加処置
1週間後に再度点検し、活動が継続している場合は再度ベイト剤を交換。2~3サイクル継続すると高確率で駆除完了します。- 補足:DIY限界を感じたら早めにプロへ切り替えを。
プロの駆除業者に依頼するメリット
- 精密調査と最適プラン提案:赤外線カメラや湿度計で被害範囲と進行度を正確に把握
- 専門薬剤と工法:残効性薬剤によるバリア工法やベイト工法で床下全域をカバー
- 侵入経路封鎖:隙間コーキングや点検口設置を含む再発防止工事も同時施工
- 保証とアフターサポート:駆除後○ヶ月の再発保証、定期点検プランあり
再発防止策と床下環境の改善
駆除後の再発を防ぐには、床下環境を整えることが不可欠です。
通気・湿気対策
- 床下換気扇の設置:湿気を強制排出し、含水率を下げる
- 基礎まわりの防湿シート:地面からの湿気をシャットアウト
侵入経路の完全封鎖
- 配管貫通部のコーキング:シリコンシーリングで微細な隙間も埋める
- 点検口の気密化:パッキンや専用蓋で外気と遮断
定期点検とメンテナンス
1年に1回程度、床下点検口から内部をチェックし、粉や蟻道、湿気のこもりを早期発見。定期メンテ契約を結ぶと費用が割安になるケースもあります。
まとめ
- 原因把握:湿気・エサ・侵入経路が巣作りを促進
- 種類理解:クロアリ/イエヒメアリ/シロアリで対策異なる
- 発見サイン:粉状排出物/蟻道/かりかり音を見逃さない
- 駆除方法選択:DIYベイト+薬剤散布 or プロのバリア・ベイト工法
- 再発防止:換気扇・防湿シート・隙間封鎖+定期点検
床下のアリの巣は放置すると建物の耐久性を脅かします。早期発見・適切な対策で、安心・快適な住環境を取り戻しましょう!